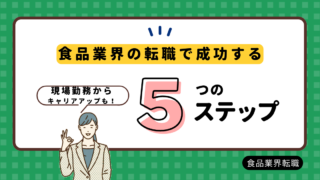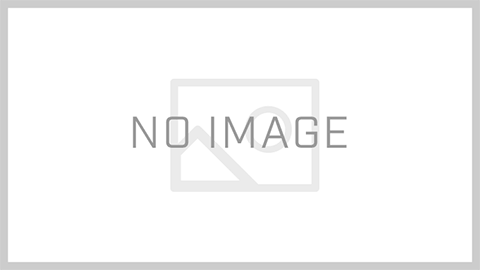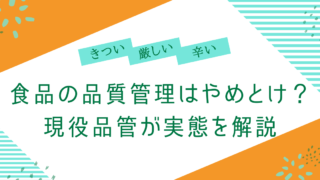食品表示チェックをやっていると、
「配合割合と裏面表示順が異なります」
ということが間々あります。
これねー、複合原材料中の添加物の扱い方で各社誤差が出ることが多いんですよね。
私も何度も消費者庁に確認しているのだけど、
食品表示基準にもQ&Aにも正答載ってないの。
「ん?この場合どうするのがいいの?」と、
疑問が出るのがレアケースなので、
文書化していないのかな?と思うのですが、
レアケースのために絶対迷うよ!
この記事を読むと、
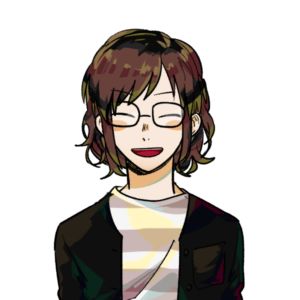
原材料名表示の記載方法の基本

食品表示基準で明確に規定されている原材料名の表示方法は5つ。
原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。
(引用:食品表示基準)
一番有名なのは、これですね。
原材料に占める重量割合が大きいものから順番に記載すること。
そして、一般名で記載すること。
上記制定が、平成2年とかなので、分類できないものもしばしばあるのだけど…。
例えばお菓子とかなら、焼チョコとか想定されておらず分類し辛いんですけどね。
1つ目を簡単にまとめると、原材料名の順位は、【重量順に一般名で書く】です。
この次は、複合原材料について難しく規定されているのだけど、かいつまむと下記の通り。
- 原材料品として加工品を使用した場合、複合原材料といって複合原材料名で記載できる。
- 複合原材料を使用した場合は、その原材料の内訳を重量順に記載する。
- 複合原材料の内訳は、5%以上含まれるものを記載。(3位以下5%未満の原材料はその他で省略可)
- 使用した複合原材料が製品から見て5%未満の場合は、複合原材料の内訳省略可。
こんな感じ。
ちなみに、原料原産地表示の対象は1番目の原材料について。
原材料名に直付けでもいいし、原料原産地と事項目を設けてもOK。

添加物表示の記載方法の基本

添加物は食品表示基準に規定されているだけでも、
かなり多くのルールがあるので、要点だけをかいつまんで。
- 製造時に投入した添加物は全部書く
- 順位付けは重量順(ただし効果を発揮する重量のみ)
- 用途名併記が必要な添加物は8種類(甘味料・着色料・保存料・増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料・酸化防止剤・発色剤・漂白剤・防かび剤又は防ばい剤)
- 14種類の用途については、同一用途の化合物を複数種使っていても1つにまとめられる(イーストフード・ガムベース・かんすい・酵素・光沢剤・香料・酸味料・軟化剤・調味料(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。)・豆腐用凝固剤・苦味料・乳化剤・水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤・膨張剤)
- 複合原材料に含まれる添加物も記載する(順位付けは投入分+複合原材料に含まれる量)
※キャリーオーバーや加工助剤で表示不要な添加物もある - 複合原材料に含まれる添加物でも、五感にかかわる添加物は省略できない(調味料・甘味料・着色料・香料など)
こんなところでしょうか。
一次ソースは食品表示基準を参照してみてください。
もっとも…添加物は細かい取り決め多く、食品添加物表示の実務なる、分厚い赤本を確認しながら日々チェックしています。
【実務】複合原材料に含まれる添加物の重量の処遇

え?これどういうこと?って思いますが、
あなたは表示を作成するとき、複合原材料の添加物の重量をどう取り扱っていますか?
というのも、
上記の通り、複合原材料に含まれる添加物は後から抜き出して別途記載します。
別途記載した際に、その重量計算はどうしていますか?
| 一次原材料 | 二次原材料 | 添加物用途名 | 配合割合 |
| 卵 | 35% | ||
| ミックス粉 | 25% | ||
| 小麦粉 | (50%) | ||
| 加工でんぷん | 製造用剤 | (15%) | |
| 粉糖 | (15%) | ||
| 米粉 | (10%) | ||
| ソルビトール | 甘味料 | (7%) | |
| 増粘多糖類 | 増粘剤 | (2.9%) | |
| 香料 | 香料 | (0.1%) | |
| マーガリン | 20% | ||
| 砂糖 | 10% | ||
| 加工でんぷん | 製造用剤 | 5% | |
| 乳化剤 | 3% | ||
| 酸化防止剤(V.C) | 酸化防止剤 | 1% | |
| 香料 | 香料 | 1% |
例なので、結構無理がある配合表ですが…
(本来ならマーガリンにも添加物含まれるはずなので)
これを表示にするとき、メーカー方針で2パターンの表示が出てくるわけです。
パターン1
卵(国産)、ミックス粉(小麦粉、粉糖、米粉)、マーガリン、砂糖/
加工でんぷん、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ソルビトール)、香料、酸化防止剤(V.C)、増粘多糖類
パターン2
卵(国産)、マーガリン、ミックス粉(小麦粉、粉糖、米粉)、砂糖/
加工でんぷん、乳化剤(大豆由来)、甘味料(ソルビトール)、香料、酸化防止剤(V.C)、増粘多糖類
え?なんで2種類??
これは複合原材料中に含まれる添加物の重量解釈の違いで生じてきます。
パターン1は単純に投入量で順位付けを行い、
パターン2は複合原材料に含まれる添加物を差っ引いた重量で順位付けを行っています。
これ、あなたはどっちの解釈で表示作ってます?
実際に、メーカーさんで見解が割れるんですよね。
結論から言えば、正答はパターン1です。
正しい表示方法は「原材料は投入量で順位付け」

投入量で原材料順位をつけ、
複合原材料に含まれる添加物は添加物の順位付けを行う上で合算はしますが、
その計算は原材料の順位付けに影響しないのです。
私も表示点検を教えてもらう際、
「製造するとき、添加物だけ抜き取って投入するって物理的に無理でしょ?」
と聞いて、確かに言われればそうなのだけど、
配合表上は2重計上になるので100%を超えてしまうという事態に。
本当に合っているのか確かめねばと思い、
消費者庁にこの解釈を支持するソースはあるのか聞いてみたのですが…。

複合原材料は添加物重量も含めた重量で順位付けをするという認識なのですが、あっていますでしょうか?




どこかに明記されているものなのでしょうか?
ですが、認識としてはあっていますので大丈夫です。

!!!!
やっぱりどこにも書いてなかった!!!
なので、直接消費者庁や保健所にこの具体的解釈を聞いたことないメーカーさんは、
「弊社は複合原材料中の添加物を差し引いて順位をつけており…」
って、言ってくるんですよね。
表示順違いませんか?って聞くと。
ある程度の解釈の違いは、会社ごとに方針があっても良いとは思うのですが、
この件はちゃんと確認すれば正しい解釈をもらえるので、
この『複合原材料の添加物の処遇問題』に出くわした際は、
毎回メーカーさんに直接消費者庁に確認するよう案内し、
正しい解釈をご納得いただき、社内方針をアップデートしてもらうようにしています。
案内したメーカーさんは、100%表示を直してくるので、
『うち間違った方の解釈やん…』とドキッとした方は、
消費者庁の表示企画課に確認をとってみてくださいね。